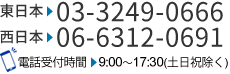今夏(2025.7)大会講演への感想として
―老舗業界で圧倒的№1成長。『情熱と論理』を両立させる、実践経営の“極意”を学びました!―
はじめに
とてつもない暑さが続いた今夏。私自身、日常生活にも大きな負担を感じましたし、
皆様の経営にも大きな影響が及んでいるだろうと想像します。気候変動の只中、従来通りが全く通用しないことを実感します。
また最近の生成AIの進展を前にして、ビジネスの在り方も、従来からの延長では到底立ち行かなくなることを痛切に感じます。
と言って、目先の業績を追った拙速経営では、早晩息詰まることも間違いないでしょう。
今こそ腹を据え、「変わること」「変わらないこと」を見極めた、「情熱と論理」を両立させた経営が求められていると思えます。
今回取り上げるのは、まさにそうした今求められる実践経営の“極意”を学ばせていただいたご講演です。
講演タイトル
「豆腐業界ダントツ№1 『相模屋』驚異の急成長戦略」
―硬直化した伝統的業界だからこそ売上22年で15倍!―
鳥越淳司氏 相模屋食料㈱ 代表取締役社長
―ピンチがチャンス、本気でやり切る!―
ご講演は、次のようなお話から始まりました。
ピンチがチャンスと言う言葉があるが・・当社は豆腐と言う伝統商品を扱っていて、
業界としては、現在ピーク時の十分の一になっている。「誰も何もやらない」状況に陥っていると言っていい。
だからチャンスがある。やれば必ず勝てる。
終わってみれば「そうやれば、誰でも出来るのはわかっていた」と言う人もいるが、
なにより「誰もやらないことをやる」ことが大事。
それは、決して「未知なこと」ではなく、誰もがやる気になればやれることで、「足元に転がっている」こと。
従来、「豆腐屋は、大きくなると潰れる!」と言われていた。100億円越えの会社はこれまで無かったが、
当社は現在年商446億円。自分が入社して22年。何しろ本気でやり切ることを旨としている!
―当社事業の基本の考え方としてー
武器は「感覚」。勘、目利き、・・数値化できないことを重視する。
1) 伝統的な豆腐を極めること
2) 伝統的な豆腐を進化させること
この両輪を回すことを狙っている。伝統の深掘りを礎にした革新の進化で市場開拓を行う。
新カテゴリーが26%、既存カテゴリーが74%。
―これまでの革新の歩み―
始まりは13年前、「ザク豆腐」。ガンダム好きの自分が欲しかった商品。
(※注:アニメ『機動戦士ガンダム』に登場するモビルスーツ「ザク」をモチーフにしたユニークな豆腐商品。
パッケージはザクの頭部を模していて、枝豆風味の豆腐が入っている。
初回限定ではザクの武器「ヒートホーク」を模したスプーンまで付けた。また豆腐を「1機」「2機」と呼んでいて、
発売から1カ月で「100万機出撃」と報じられたほどの人気ぶりだった・・・とのこと。)
何より、豆腐業界、はじめての商品。
1)(豆腐業界で)はじめて30~40代男性をターゲット。
2)はじめて、何もつけずにそのまま味わえる豆腐。
3)はじめて、一丁丸ごと食べておいしい豆腐。
豆腐業界で初めてターゲットを絞った。それがヒットした一番の要因。
木綿・絹以外の豆腐でも売れることが分かったことも大きい。
そこで次は「ビヨンド豆腐(BEYOND TOFU)」。
(※注:「ビヨンド(Beyond)」は英語で「超える」という意味。「豆腐を超えた豆腐」というコンセプトで、
豆乳クリームという特別な素材を使って、従来の豆腐の枠を飛び越えた食感や風味まで再現しているのが特徴)
20代の女性層にチャレンジ。ファッションショーでもPR。結果、お豆腐に若い女性の大行列が出来た。
PBF…植物性由来の原材料を使った食物が着目される時代になってきたことが大きい。
お豆腐こそ、ぴったりの食べ物。ビヨンド豆腐で、ウニ、白子、フォアグラに近い食べ物を作っている。
確かに、言われてみれば誰でも出来そうですが、実際に実行し成功するのは、とんでもなく難しい。
常識を超えた発想と創意工夫が必要ですし、粘り強くやり切っていく信念がなにより大事と思います。
ご自身の思い込みを信じて事業を進めている姿が、経営者としてカッコよく素晴らしいと思いました。
後半は、地方の老舗豆腐店の再建のお話でした。そこには、独自な組織戦略が組み込まれており、
「なるほど、そういうやり方を取っているのか!」と、まさに“目から鱗”になってお聞きしました。
―破綻しかけた地方の豆腐屋さんを救済するー
各地方に根付いた独特の豆腐文化と独自の豆腐作り。その地方の独自な豆腐文化を守ることを使命に、この事業を始めた。
12社すべて黒字化、6社債務超過解消。SOSが上がった全ての会社を救済する方針でやっている。
最近は、地方の豆腐の雄が倒産している。原因は終わりなき価格競争!規格化均質化で個性を捨て、
どこも一緒なので価格以外の差がなくなる。だからこそ、“個”を大事に、その“個”を取り戻すことにこだわる。
改革は次の4つのステップで行っている。
1)大破綻時代 →2)救済M&Aと再建融和 →3)“技”の結集としてのグループ化 →4)脱常識、独自性こそ正義、にシフト。
そして再建のために、次の3つのことを決めている
1) 再建会社の“個”を伸ばす
2) 相模屋色はつけない
3) 再建先の人材で、再建する
一方、再建の進め方としては、「N字再建」を取っている。
①はじめは既存設備と既存人材で、まずは黒字化。
・三分の二の、どこにでもある商品を捨てる。
・三分の一の独自商品に特化する。
売上は落ちるが、おいしさは復活。シンプルなこと。
そして過去のやり方を思い出させ、黄金時代を取り戻す。
その結果、社員がやる気を取り戻し、モチベーションが高まっていく。
②次に大型設備投資をおこなう。
・一旦は赤字化する。
③黒字化へ(地域商品から広域商品になり、売上大幅アップ)
この二年で5社は性急すぎないか、と言う意見もあるが・・スピードを重視している。
考えられるリスクとして
1)人材リスク 2)インフラリスク(生産設備など・・) 3)兵站リスク
しかし、救済再建であれば、いずれも対応可能。
破綻する会社には、カスしか残っていない、と勘違いしている人も多いが、そんなことは無い。
1)人材リスクに対しては
・「モノづくり人材体制」に絞り込み、限定する。間接部門はいらない。(コストもカット)
販管部門を相模屋本社に集約。「廃藩置県方式」を取っている。お殿様はいらない。
再建会社の現地人材を主役に、他人事ではなく自分事にする。
『自分達だけでやる、自分たちが主役だ!』と言う意識を持たせる。
ダメな破綻会社だからと言って、ダメな従業員ではない!
・相模屋からは誰も常駐しない。「訪問診療方式」。
「再建プロジェクトチーム、7人の侍」で指導・育成を進める。
毎週訪問して、現地指導。プラス、日々のネットなどでのやり取り。
「最重点先」「近郊エリア」「巡航先」と区別して、クラス分けして支援。
ステージの違いで支援の中身を変えている。
例:ER(緊急救命室)➡ICU(集中治療室)➡一般病棟➡通常生活
<その狙いとメリット>
1)現地人材のモチベーションアップ
→結果として改善スピートが大幅アップし、ガバナンスもOK
2)最高レベルの改善指導を全工場に浸透させる。改善スピードMAX化。
3)グループの一体感アップ(エース級が来ることで、より一体感が高まる)
結果として、再建チームのノウハウも上がってくることになる。
2)インフラリスクに対しては
・再建会社の既存設備の活用を大前提。ぼろぼろの工場設備でも、ちょっと修理すれば使える場合が多い。
その目利きのノウハウを磨くことが大事。そうすれば、現地人材による運用もスムーズにできる。
3)兵站リスクに対しては
・何より相模屋本社の営業力。18人の営業担当者が、再建会社の商品を自社商品として売り込む。
これまで地域商品だったものを、新しい商品として全国広域商品にする。販路エリアが大きく広がる。
結果として、売上が大きく上がることになる。
理論は後付けであるべき。必死に考えて全力でやり切りました。そのおかげで成功しました。
ふと振返ったら、そのことは理論に則っていました、と言う事だろう。
ヒット商品は、“思い付き”からはじまる。
居酒屋での飲み会の“思い付き”を、本気で実現しようとすること。
完璧を目指さない。5割で十分。その代り全力で!
(ガンダムの)ジオングに、足無しで出せるかどうか、足なんて必要ないよ!と言って戦えるか?ということ。
とても熱い思いを込めたご講演でした。
後半の老舗企業の再建は、今まで全く聞いたことのないトータルな実践論として、とても勉強になりました。
「老舗企業の再生」「地方再生」等、いろいろなケースでとても参考になる有効な戦略方法論と思います。
最後のガンダムの落ちは、熱烈なファンならではお言葉ですね。
鳥越社長には、大変ありがとうございました。
文責:株式会社CBC総研 山川裕正氏
(講演依頼サイトの講師SELECTにとびます)
講師SELECT 山川裕正氏 プロフィール(講演依頼サイトの講師SELECTにとびます)